
DAY 11:ボリンジャーバンド – ボラティリティを把握
FX
前回(DAY 10)はMACDの仕組みと活用法を学びました。
今回は、相場の“ボラティリティ(変動幅)”を可視化する指標として有名なボリンジャーバンドを扱います。
ボリンジャーバンドは、トレンド相場でもレンジ相場でも多様な戦略を立てやすく、初心者から上級者まで幅広く使われています。
さっそくその仕組みと使い方を見ていきましょう!
1. ボリンジャーバンドとは?
- 開発者:ジョン・ボリンジャー
- 基本構造:移動平均線(通常はSMA)に対して、標準偏差を加減した“バンド”を描画することで、価格が“平均からどの程度離れているか”を視覚化する。
- 通常の表示:±1σ、±2σ、±3σなど複数のバンドがチャート上に描かれ、価格がどのバンド付近に位置しているかでボラティリティを判断する。
(1) 標準偏差とは?
- 過去の値動き(終値など)のデータから導き出された“散らばり具合”。
- 値動きが大きく変動していれば標準偏差は大きくなり、バンドの幅が広がる。
- 値動きが狭いレンジに収まっていれば標準偏差は小さくなり、バンドの幅が狭くなる。
2. ±σ(シグマ)の意味
(1) ±1σ(約68%)
- 移動平均線から上下に1σを加減したバンド。
- 過去の統計的には、価格が約68%の確率で±1σの範囲内に収まるとされる。
(2) ±2σ(約95%)
- 一般的によく使われるのが±2σ。
- 価格が約95%の確率で±2σ内に収まると言われており、逆張り戦略の目安にするトレーダーも多い。
(3) ±3σ(約99.7%)
- ±3σまで価格が到達するのは、統計的にはかなり稀。
- とはいえ、市場が極端な“バンドウォーク”状態(後述)に陥ると意外に到達することもあり、油断は禁物。
3. スクイーズ&エクスパンション
(1) スクイーズ(Squeeze)
- ボリンジャーバンドの幅が“キュッ”と狭くなる状態。
- ボラティリティが低下している=「エネルギーが溜まっている」サインとも言われ、後に大きなブレイクが発生することが多い。
- スクイーズを確認してから“ブレイク狙い”のエントリー準備をする戦略が一般的。
(2) エクスパンション(Expansion)
- バンド幅が“グワッ”と広がる状態。
- ボラティリティが急上昇=価格が大きく動き始めている状況。
- 強いトレンドが発生している可能性が高く、“バンドウォーク”と呼ばれる現象が起こることがある。
(3) バンドウォーク
- 価格が±2σや±3σなどの外側バンドに沿って動き続ける現象。
- 一般には「±2σをタッチすると反発する」という逆張りセオリーが有名ですが、強いトレンド時はタッチするだけでなく、そのまま外側を歩き続けてしまう(=バンドウォーク)ため大きな損失を招くことも。
- つまり、**“逆張り”だけでなく“バンドウォークに乗って順張り”**という発想も必要。
4. ボリンジャーバンドの代表的トレード戦略
(1) 逆張り戦略
- 価格が**±2σや±3σ**にタッチ(あるいは飛び出る)
- 相場が行き過ぎと判断し、“反発”を狙って逆張りエントリー
- 損切りは、さらにバンドウォークへ発展した場合を想定して、外側バンドの少し外側に置く
- 利確目標は移動平均線付近 or ±1σ付近など
注意点:
- 上昇トレンド中なら、-2σタッチでの逆張り買いは有効かもしれないが、+2σタッチでの逆張り売りは踏み上げられるリスクがある。
- 強いトレンドがあるかどうかを、**移動平均線の傾きや他の指標(MACDなど)**で確認すると◎。
(2) 順張り戦略(ブレイクアウトやバンドウォーク狙い)
- スクイーズ後にバンドが急にエクスパンションし始め、価格が外側のバンドに触れて推移し始める
- これは相場のボラが急増=トレンドが発生した可能性が高い
- “ブレイクアウト”を狙う順張りエントリーで、バンドウォークに乗る戦略
- バンド内に戻ってきたら手仕舞いするなどの明確なルールがあると損失を最小化できる
(3) 他のテクニカルとの併用
- ボリンジャーバンドだけで判断するより、MACDやRSIでトレンドや勢いを確認しながらエントリーを絞り込む人が多い。
- 裁量トレードでは、「±2σタッチ+RSIが売られすぎ」のように複数条件が合致したポイントを狙うと信頼度が上がりやすい。
5. ボリンジャーバンドのメリット&デメリット
メリット
- ボラティリティの可視化
- スクイーズ状態は“次に大きく動きそう”、エクスパンション状態は“勢いが強い”といった判断がしやすい。
- 逆張り&順張りの両戦略に対応
- ±2σを使った逆張りだけでなく、バンドウォークに沿った順張りも狙える。
- 多彩な設定
- デフォルトは20期間・±2σが多いが、自身のトレードスタイルや時間軸に合わせて期間や標準偏差を調整可能。
- デフォルトは20期間・±2σが多いが、自身のトレードスタイルや時間軸に合わせて期間や標準偏差を調整可能。
デメリット
- 強いトレンドに対する逆張りは危険
- “行き過ぎ”だと思って逆張りしたら、そのままバンドウォークで突き抜けるケースがある。
- 過剰な期間調整やカスタマイズで迷走する可能性
- 期間やσをいじりすぎると過去データに最適化しすぎて、リアルトレードでは通用しないことも。
- “反発のタイミング”の見極めが難しい
- バンドにタッチした瞬間がベストエントリーとは限らず、もう一押しあるかもしれない。
- エントリー時期を遅らせる or 分割エントリーで対処するなどの工夫が必要。
6. まとめ & 次回予告
まとめ
- ボリンジャーバンドは移動平均線を中心に、価格の標準偏差を可視化する優れた指標。
- スクイーズ→エクスパンションという流れは、相場の“エネルギー充填→放出”を示唆しており、ブレイクアウトを狙う好機が生まれやすい。
- 逆張り戦略は±2σや±3σで反発を狙うが、強いトレンドでは「バンドウォーク」で大きく踏み上げられるリスクがある。
- 他のテクニカルやプライスアクションと併用し、“逆張りor順張り”を状況に応じて使い分けるのがポイント。
次回(DAY 12)のテーマ:一目均衡表 – 日本生まれの総合分析ツール
- ついに日本が誇る総合指標、一目均衡表に進みます。
- 基準線、転換線、雲など一つひとつの意味を整理しながら、トレンド・相場の強弱を把握する方法を解説。
- 海外でも評価が高い一目均衡表は、裁量トレーダーだけでなくアルゴでも取り入れる人がいるほど奥が深いです。ぜひお楽しみに!
自動売買に興味がある方は↓コチラもよろしくお願いします。
https://www.gogojungle.co.jp/users/147322/products
お役に立ちましたら、「続きを読む」を押して頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
×![]()


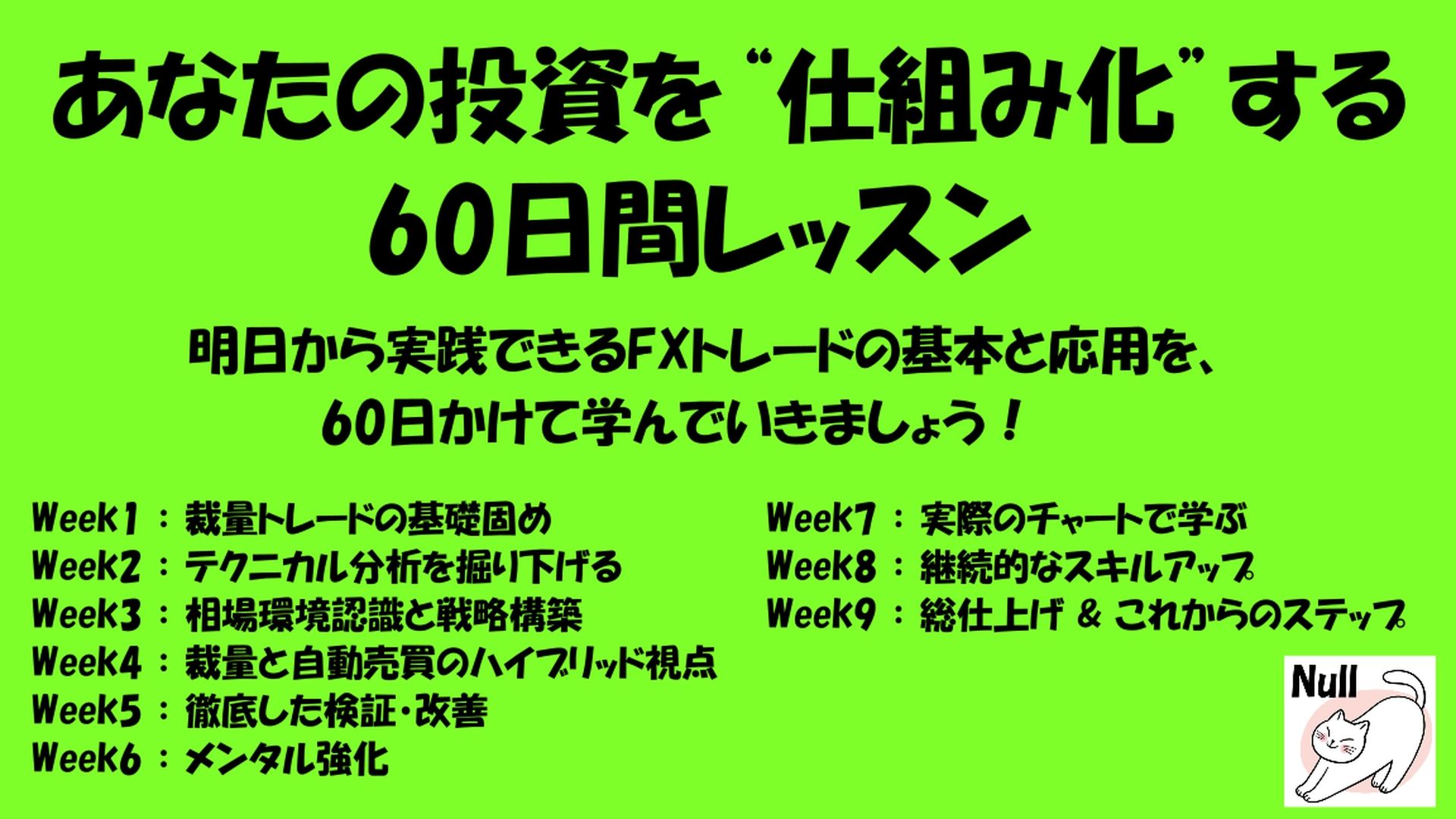
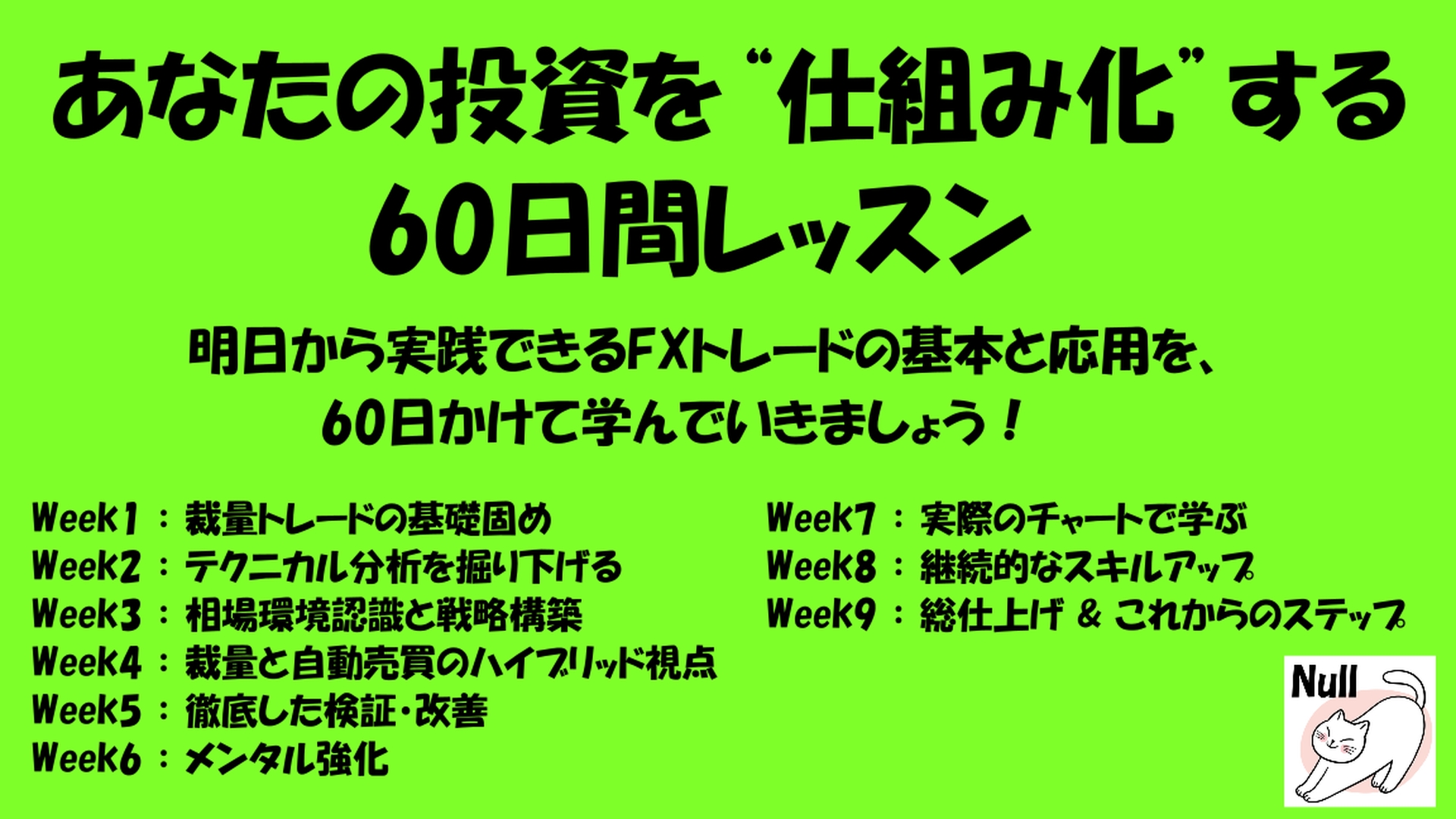
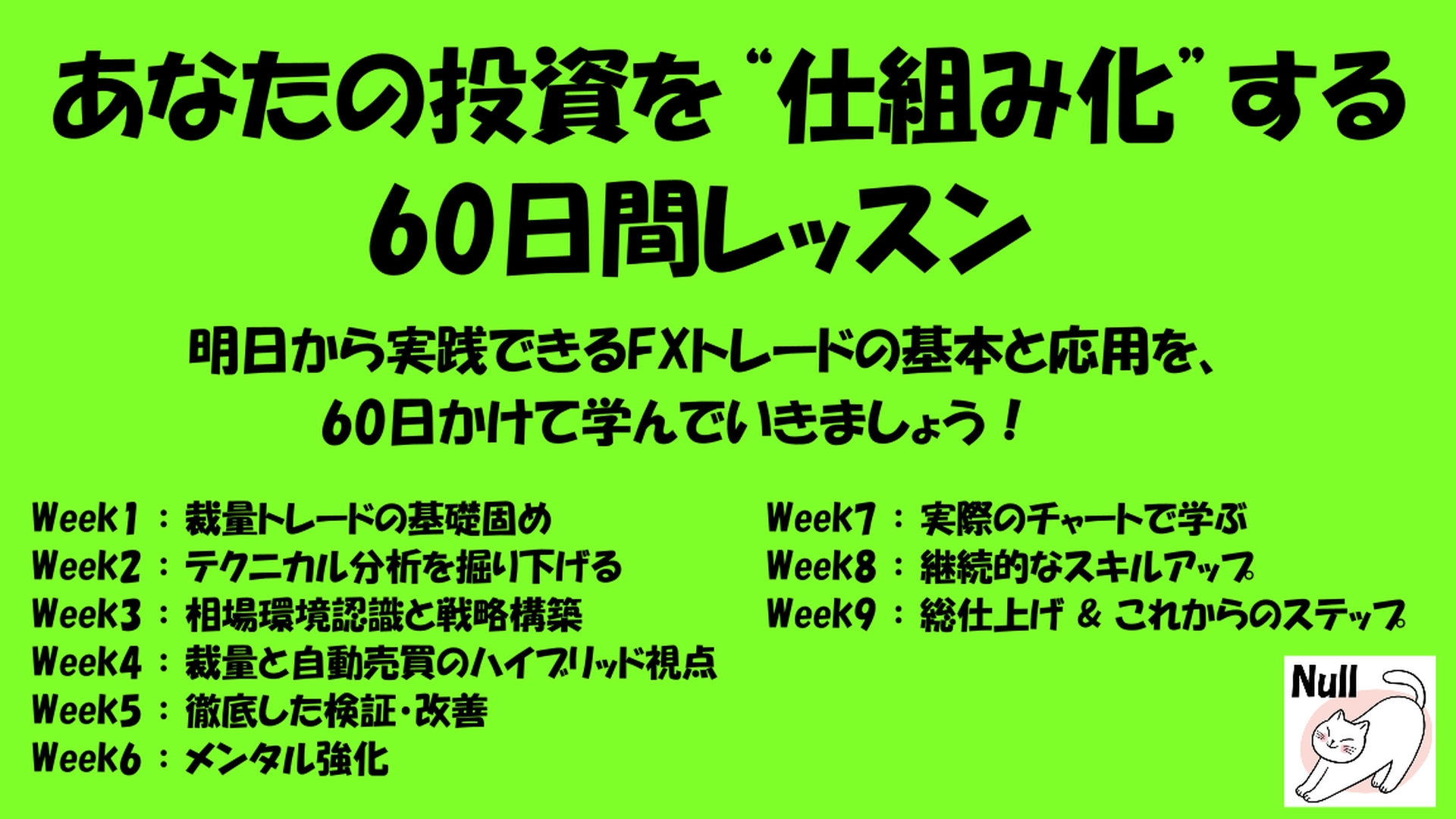
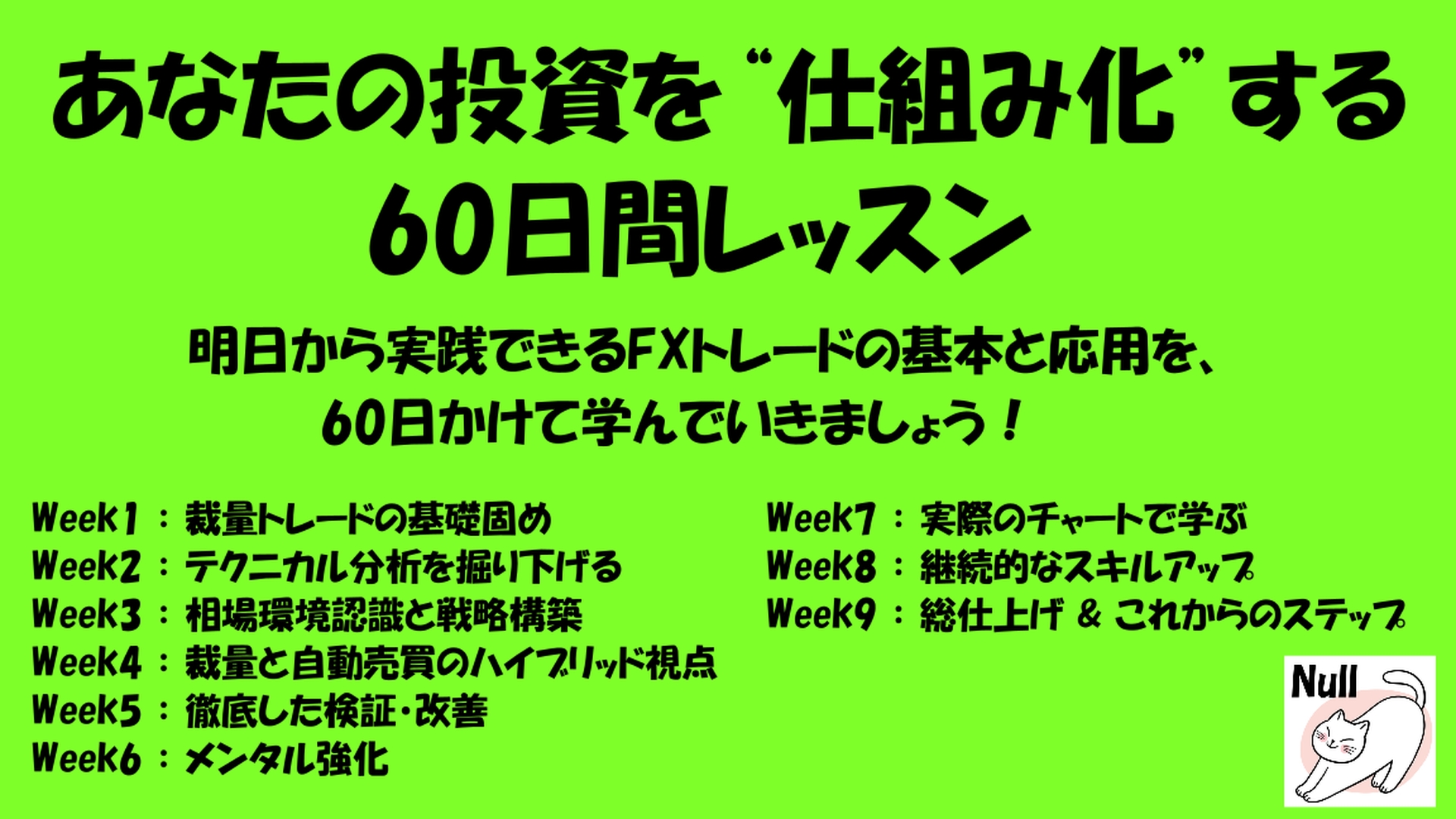
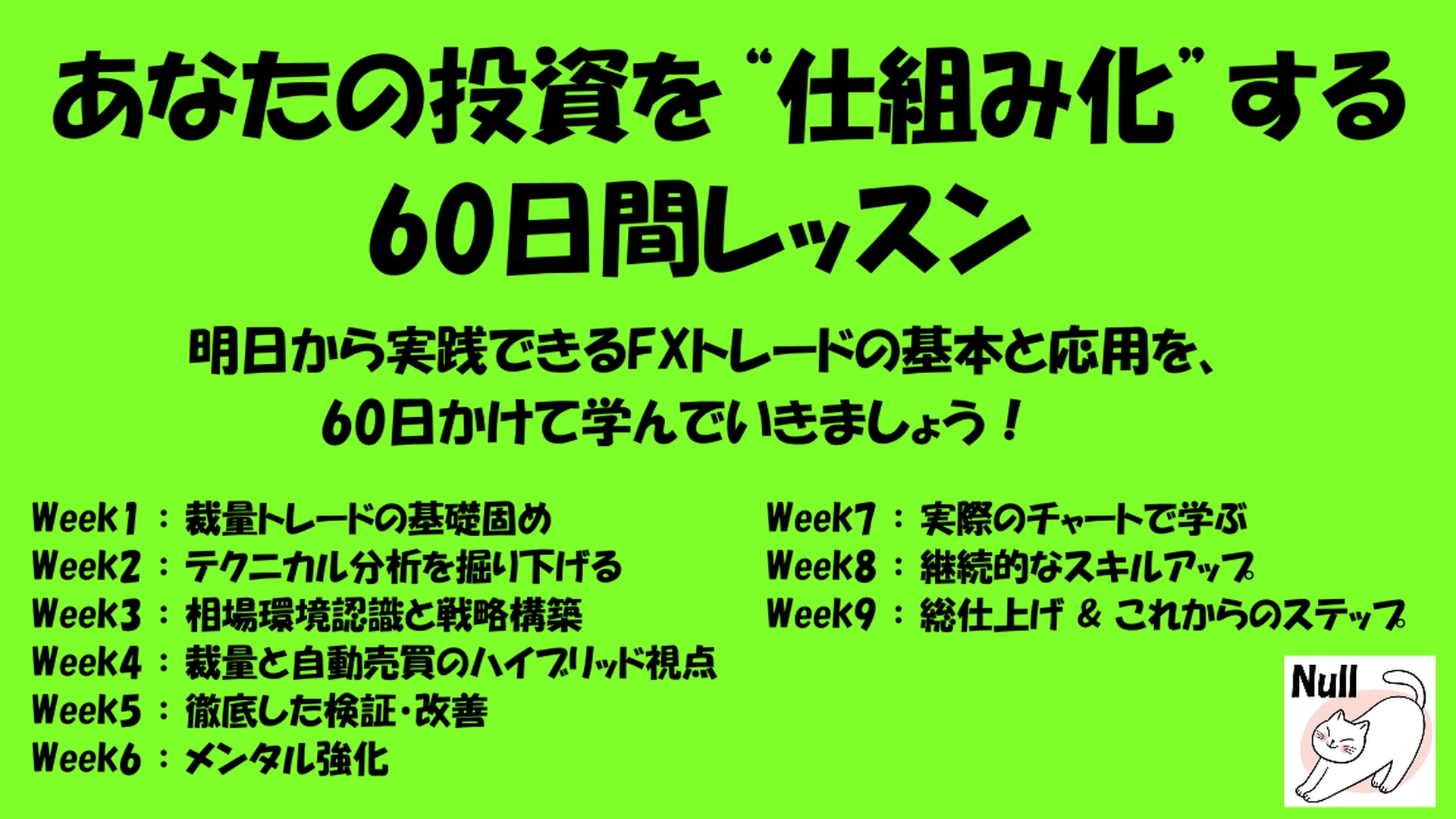
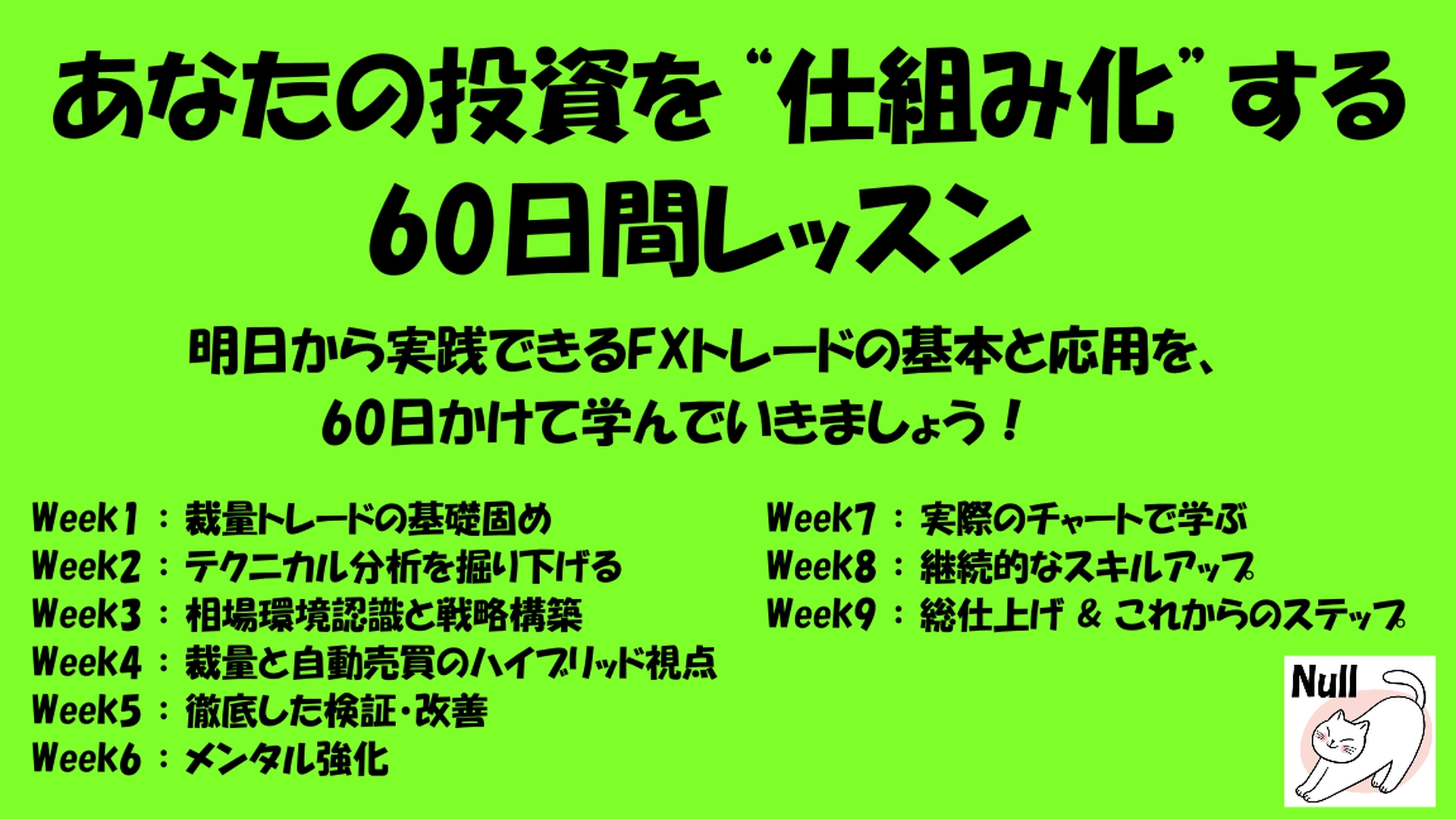
Is it OK?