
DAY 10:MACD – トレンドと勢いを同時にチェック
FX
DAY 9では、RSIとストキャスティクスといった“オシレーター系指標”を学びました。
今日は、そのトレンド分析とオシレーター分析をあわせ持つ人気のインジケーター、**MACD(Moving Average Convergence Divergence)**をご紹介します。
MACDは、トレンド方向の把握からタイミングの判断、さらにはダイバージェンス検知による反転予測まで、多角的に使える強力なツールです。早速、その仕組みと活用法を見ていきましょう!
1. MACDの基本構造
(1) MACDライン&シグナルライン
- MACDライン
- 2本の移動平均線(一般に短期EMAと長期EMA)を使った計算で導かれるライン。
- 短期EMAが長期EMAより上回っていればMACDは正の値、下回っていれば負の値となり、“トレンドの強弱”を示す。
- シグナルライン
- MACDラインをさらに平滑化(移動平均)したライン。
- MACDラインがシグナルラインを上抜け(もしくは下抜け)するポイントが売買シグナルになりやすい。
(2) ヒストグラム表示(MACDヒストグラム)
- チャートによっては、“MACDライン − シグナルライン”の差を棒グラフ(ヒストグラム)で表示するタイプがある。
- ヒストグラムがプラス圏ならMACDラインがシグナルラインを上回っている、マイナス圏なら下回っている状態。
- ヒストグラムが拡大・縮小する動きで、勢いが増しているか、減速しているかが一目でわかります。
2. 代表的な使い方
(1) MACDラインとシグナルラインのクロス
- 買いシグナル:MACDラインがシグナルラインを下から上へ突き抜ける(ゴールデンクロスに似たイメージ)。
- 売りシグナル:MACDラインがシグナルラインを上から下へ突き抜ける。
注意点:
- 「クロスした=即エントリー」という単純ルールはダマシも多い。
- クロスする前後の価格推移や、直近高値・安値付近での動きなど、ほかの指標やプライスアクションをあわせて確認しましょう。
(2) ゼロライン(基準ライン)の突破
- MACDラインがゼロラインを上抜いたら、上昇トレンドが加速している可能性がある。
- ゼロラインを下抜いたら、下落トレンドが加速している可能性がある。
- 特にヒストグラムがゼロライン付近から一気に拡大するパターンは、勢いが強まっているサイン。
(3) ダイバージェンス
- 価格が高値更新(もしくは安値更新)しているのに、MACDは更新できずに反転する例。
- MACDダイバージェンスは、トレンド転換の事前シグナルとして注目度が高い。
- ただし、ダイバージェンスが出てもすぐ反転とは限らないため、タイミングの測定がポイント。
3. トレンド・オシレーター両面の特徴
MACDは“移動平均”をベースにしているためトレンド系の要素が強いですが、
- クロスやダイバージェンスのサインはオシレーター的なタイミング取りに使える。
- トレンドの方向性と勢いの強弱の両方を、1つの指標でチェックできるのが大きなメリットです。
4. トレードシナリオの例
(1) 上昇トレンドでの押し目買い
- MACDラインがゼロラインより上 → 上昇トレンド中
- 一時的な押し(価格の下落)時にMACDラインがシグナルラインを下回るが、再度クロスして上に抜き返したら“買いサイン”
- 損切りは直近安値やサポートライン付近、利確目標はMACDやヒストグラムの伸びが鈍化してきたタイミングなどで検討
(2) レンジ気味の相場でダイバージェンスを狙う
- 価格の安値が切り下がり続けているのに、MACDラインの安値が切り下がらなくなった → 底打ちの可能性を示唆
- 移動平均線の傾きがフラットなら、MACDダイバージェンスで短期の反転狙いも有効
- 損切りラインはダイバージェンスが否定された時点(安値更新が続いた時など)に設定
(3) 自動売買での活用
- MACDクロスだけでエントリーと決済を繰り返すEAなども多く存在。
- ただし“クロス後に大きく逆行”する相場もあるため、フィルター(移動平均線の傾き、ボリンジャーバンドの位置など)を加えるのが一般的。
5. MACDのメリット&デメリット
メリット
- “トレンド系”と“タイミング系”の両方の性質
- これ1つで大まかなトレンドとエントリーポイントを把握できる。
- シンプルな計算式
- 移動平均線ベースなので理解しやすく、初心者でも使い始めやすい。
- ダイバージェンスが視覚的にわかりやすい
- ヒストグラムの拡大・縮小で勢いの変化も一目瞭然。
- ヒストグラムの拡大・縮小で勢いの変化も一目瞭然。
デメリット
- 遅行性
- 移動平均線ベースなので、急な価格変動への反応はワンテンポ遅れる。
- クロスだけでの判断はダマシが多い
- ローソク足のプライスアクションや他の指標と組み合わせて総合判断をする必要がある。
- 最適なパラメータが相場により変化
- 一般的には「12, 26, 9」がデフォルトだが、通貨ペアや時間足、相場状況で微調整が必要になる場合も多い。
- 一般的には「12, 26, 9」がデフォルトだが、通貨ペアや時間足、相場状況で微調整が必要になる場合も多い。
6. まとめ & 次回予告
まとめ
- MACDは移動平均線を元にした、トレンド把握×売買タイミング確認ができる人気指標。
- MACDラインとシグナルラインのクロス、ゼロライン突破、ダイバージェンスなど、活用ポイントが豊富。
- 遅行性やダマシへの対策として、他のテクニカルやプライスアクションとの併用が理想。
- 自動売買(EA)でもよく使われるが、パラメータ設定とフィルター条件が勝敗を分けやすい。
次回(DAY 11)のテーマ:ボリンジャーバンド – ボラティリティを把握
- トレンド系&オシレーター系を学んだところで、今度は**ボラティリティ(価格の変動幅)**を可視化する人気指標、ボリンジャーバンドに進みます。
- “スクイーズ”と“エクスパンション”の概念、±2σ付近を使った逆張り・順張り戦略など、幅広い活用法を解説していきます。
- ここまで学んできたMACDやRSIとも相性がいいので、さらに多面的な分析力を磨いていきましょう!
自動売買に興味がある方は↓コチラもよろしくお願いします。
https://www.gogojungle.co.jp/users/147322/products
お役に立ちましたら、「続きを読む」を押して頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
×![]()


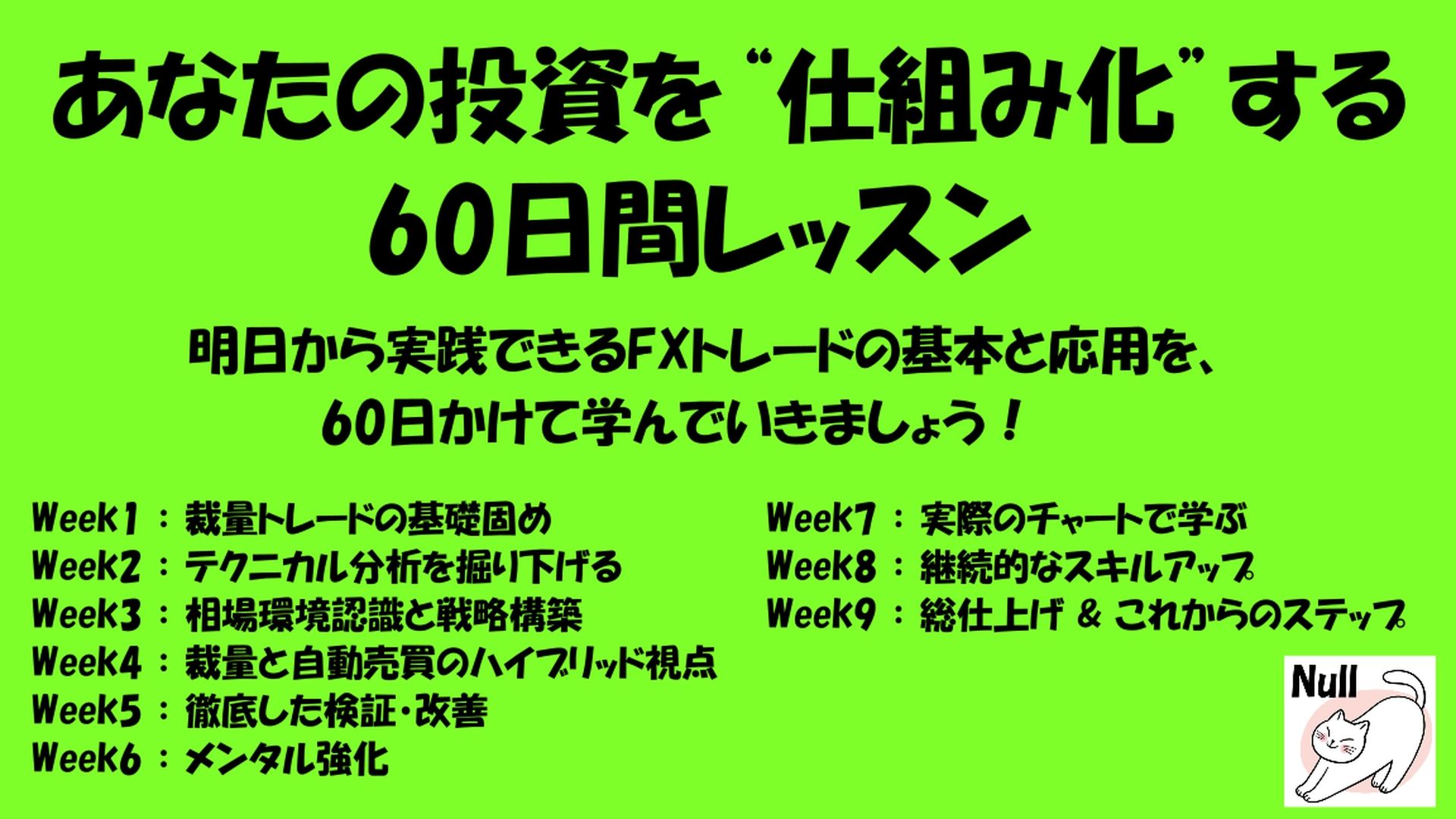
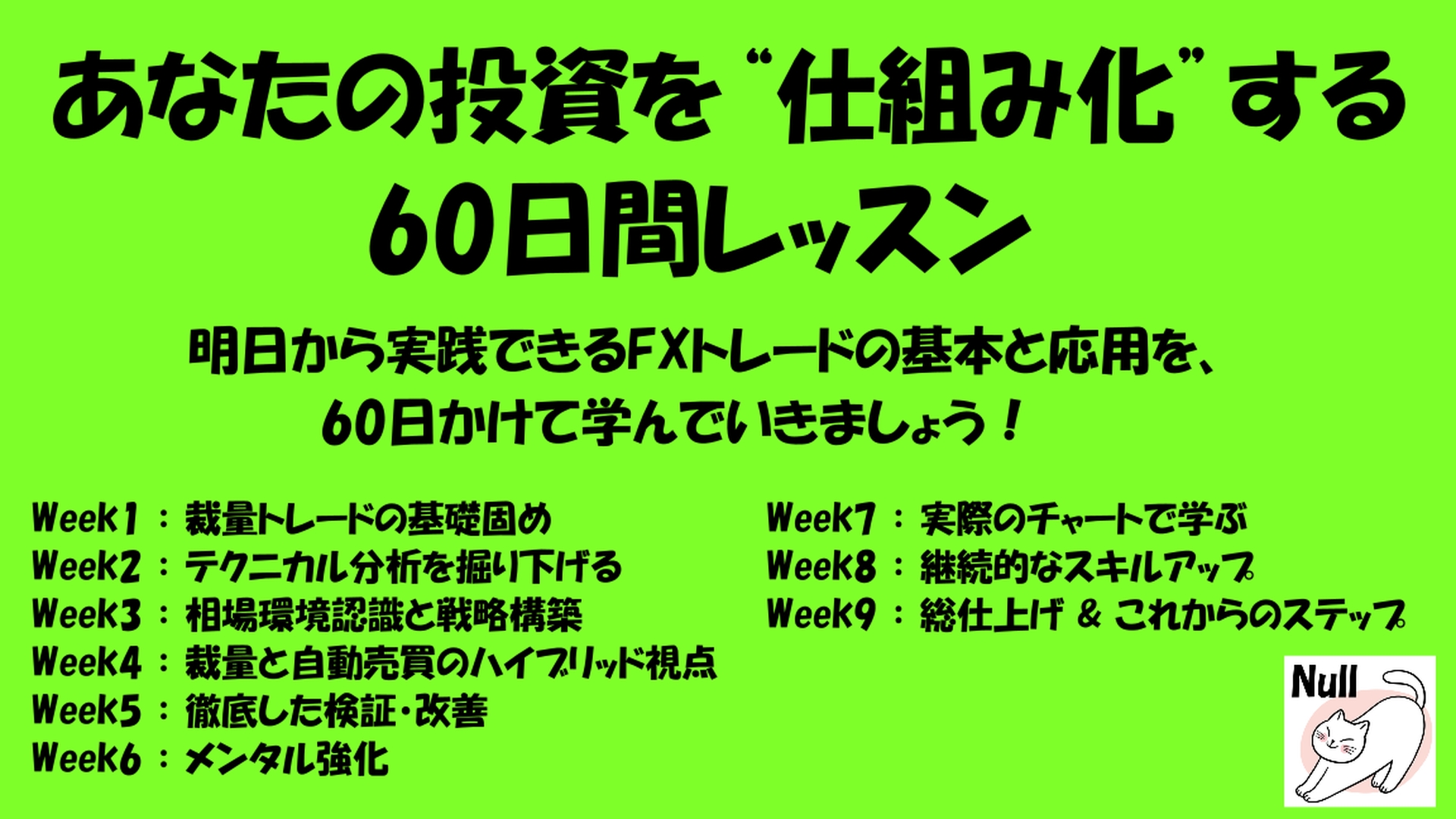
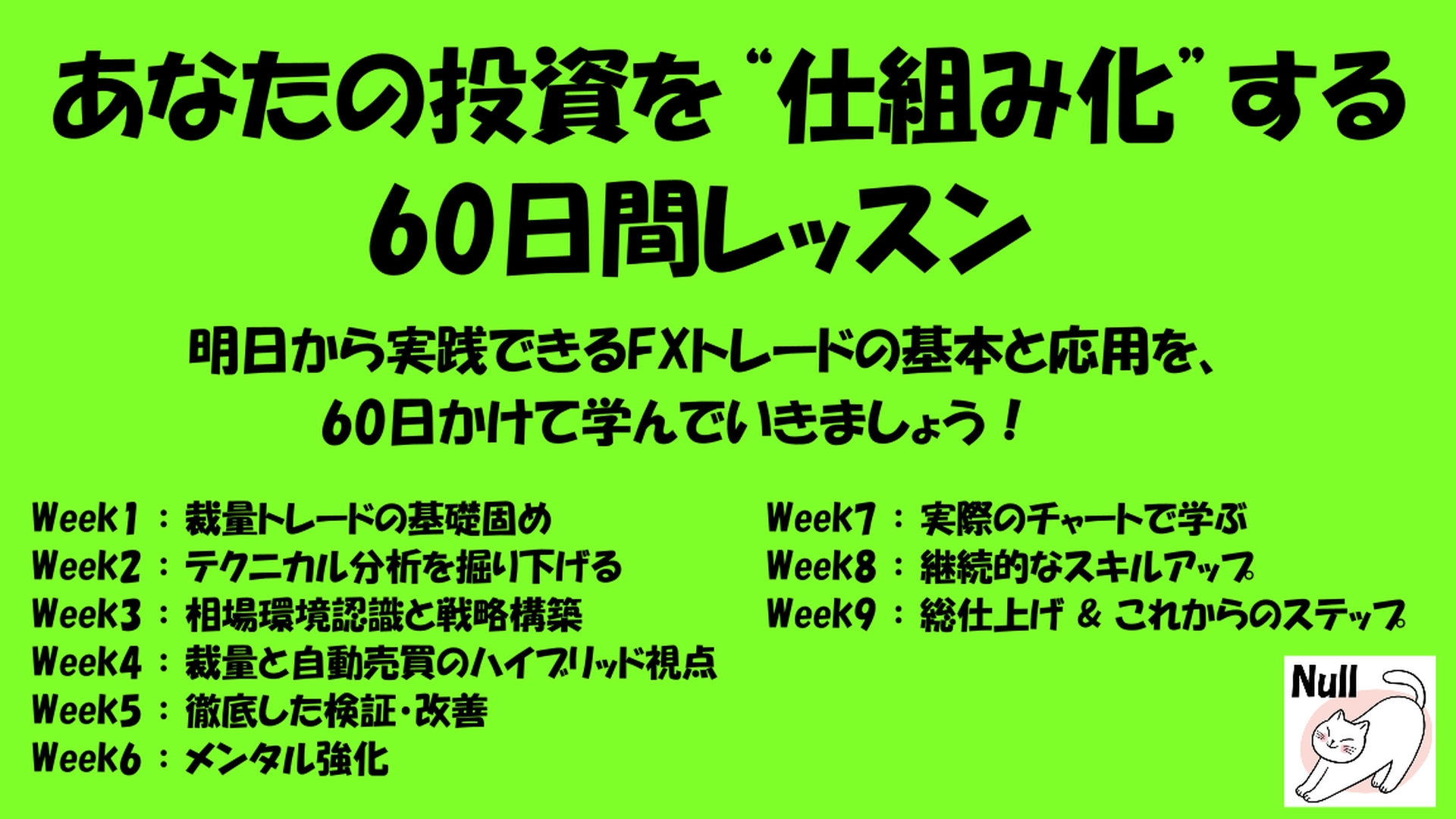
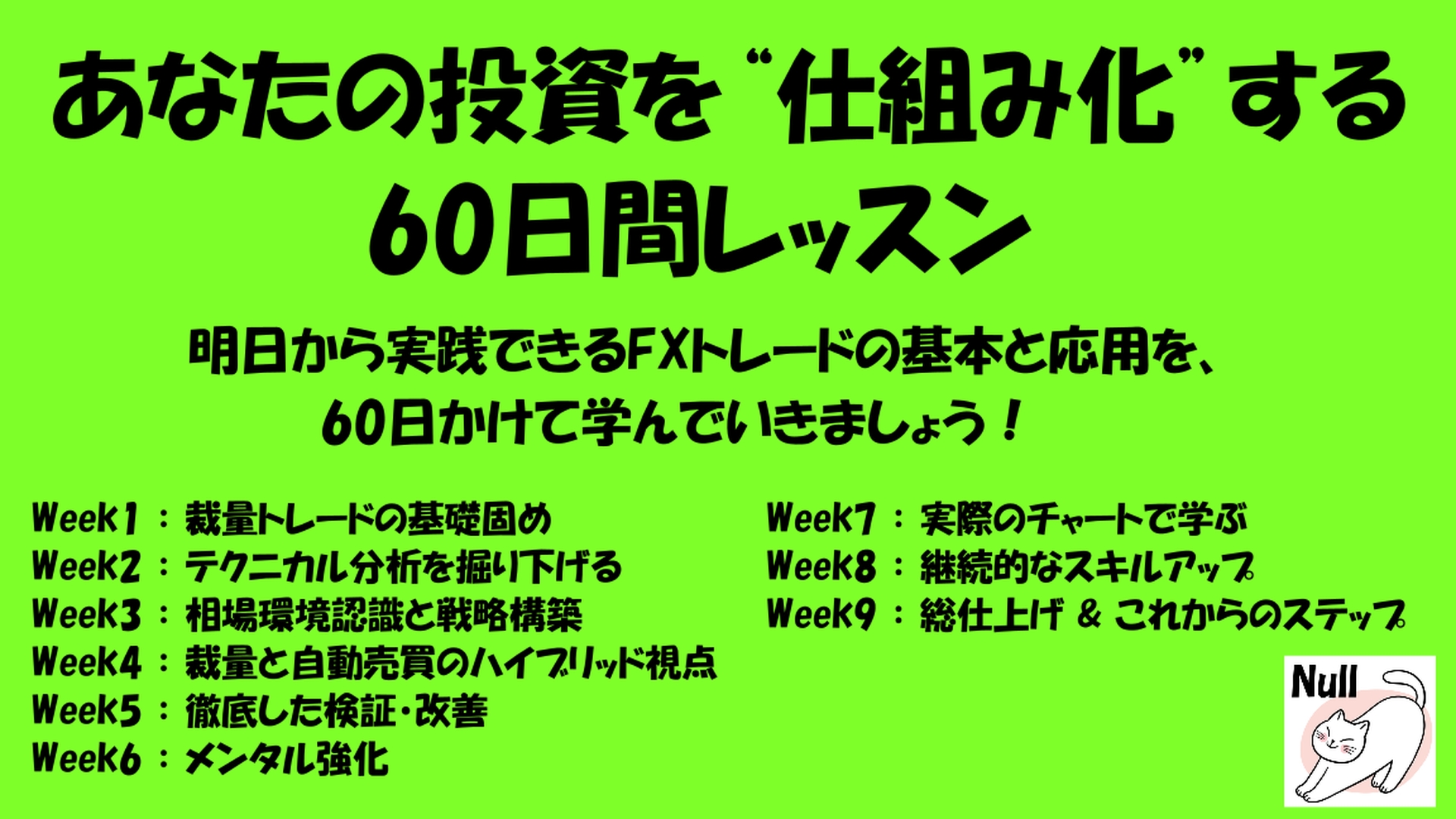
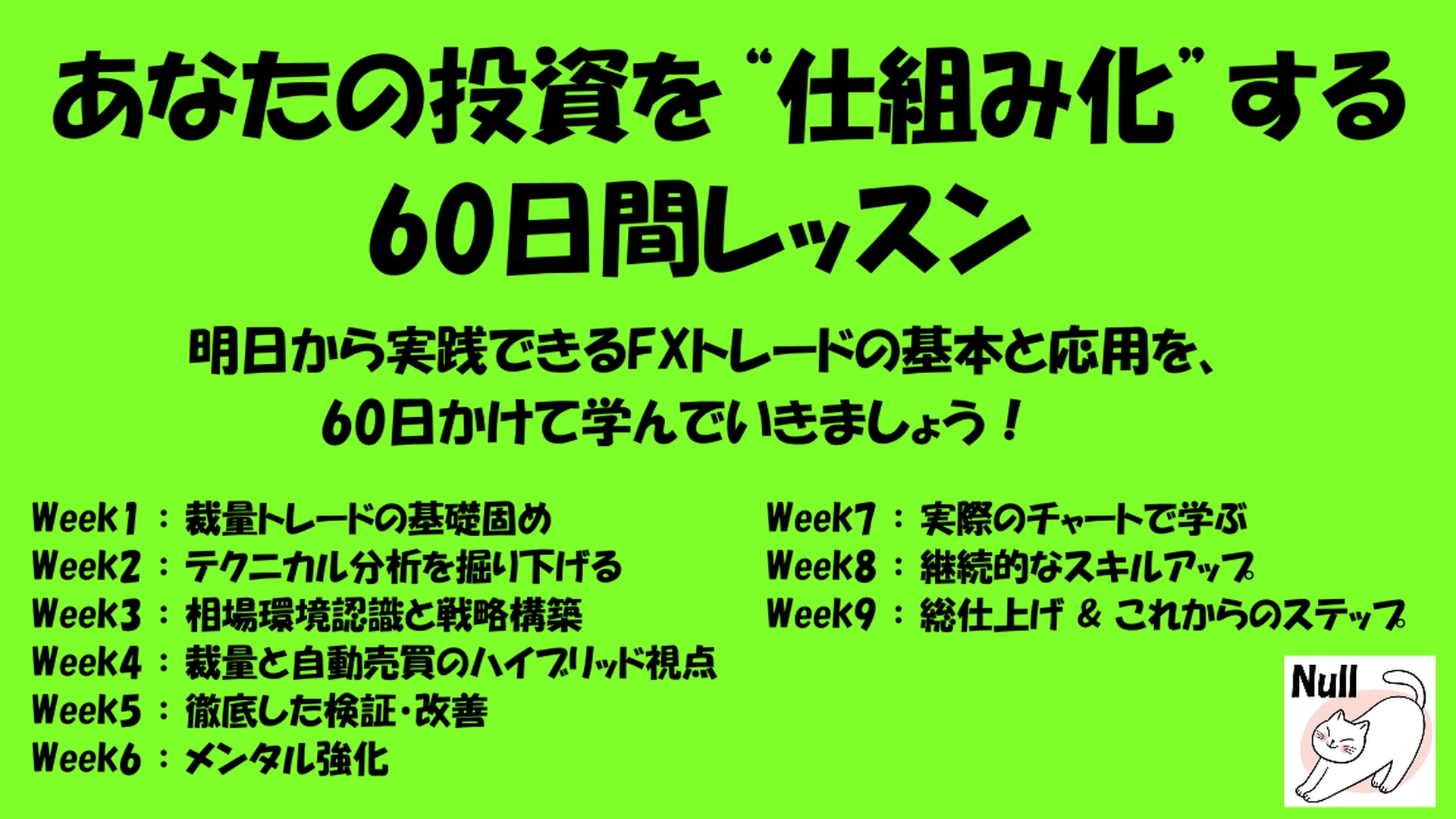
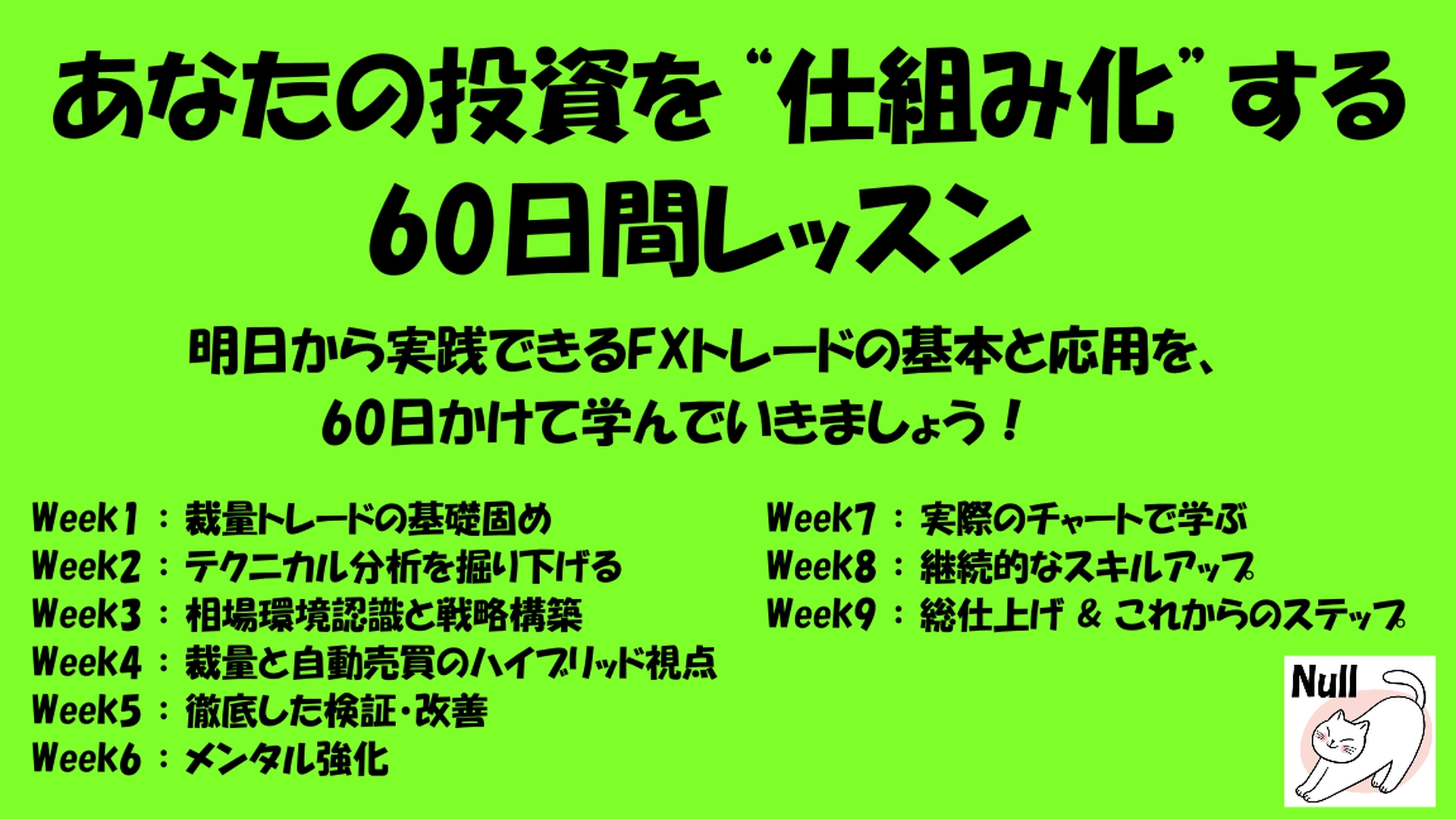
Is it OK?