
DAY 9:オシレーター – RSIとストキャスティクスの基本
FX
前回(DAY 8)では、移動平均線を使ったトレンド分析を学びましたね。
今回は、相場の“勢い”や“買われすぎ・売られすぎ”を把握するために使われるオシレーター系インジケーターの代表格、RSIとストキャスティクスを解説します。
どちらも初心者からプロトレーダーまで幅広く使われていますが、単純に「数値が○○だから買い/売り」というだけではダマシも多いもの。しっかり基本的な考え方と応用的な使い方を押さえていきましょう。
1. オシレーター系指標とは?
- オシレーター系指標:価格や出来高などを数値化し、一定範囲内(例:0~100)で推移するように表示されるインジケーター。
- 主に、買われすぎ/売られすぎを判断したり、相場の“勢い”や“反転のタイミング”を探るために用いられます。
- 移動平均線などのトレンド系指標と併せて使われることが多く、トレンド相場では押し目や戻りのポイント、レンジ相場では逆張りポイントを見つける際に有効。
2. RSI(Relative Strength Index)
(1) RSIの基本的な仕組み
- 計算式(詳細は割愛)
- 一定期間内の上昇幅・下落幅を比較し、「相場がどれだけ強い買い圧力/売り圧力を受けているか」を数値化。
- 値の範囲
- 0~100の範囲で推移。一般的には**70以上で“買われすぎ”、30以下で“売られすぎ”**と判断する。
- 0~100の範囲で推移。一般的には**70以上で“買われすぎ”、30以下で“売られすぎ”**と判断する。
(2) 一般的な使い方
- 逆張りの目安
- RSIが70を超えると、短期的には上昇しすぎている可能性が高い。
- RSIが30を割ると、短期的には下落しすぎている可能性が高い。
- そのため、「70超えで売り検討」「30割れで買い検討」がよく紹介される。
- ダイバージェンスの活用
- 価格が高値更新しているのにRSIは高値を更新しない(または安値が切り下がっていない)状態 → “ダイバージェンス”と呼ばれ、相場の勢いが衰えてきたサインとも言われる。
- RSIだけでなくストキャスティクスなど、オシレーター全般で利用可能な分析。
(3) 注意点
- トレンド相場では“買われすぎ”でもさらに上昇し続けるケースあり
- RSIが70を超えたからといって即座に売りで入ると、強い上昇トレンドでは痛い目に合うことがある。
- 期間設定で使い勝手が変わる
- 一般的には14期間がデフォルト設定だが、5や9、21など自分に合う期間を試してみるとよい。
- 一般的には14期間がデフォルト設定だが、5や9、21など自分に合う期間を試してみるとよい。
3. ストキャスティクス(Stochastics)
(1) ストキャスティクスの基本的な仕組み
- 計算イメージ
- 一定期間の最高値と最安値の範囲内で、現在価格がどのあたりに位置しているかを数値化。
- “%K”や“%D”というラインがあり、これらの動きで買われすぎ/売られすぎを判断する。
- 値の範囲
- 一般に0~100で表示され、80以上が買われすぎ、20以下が売られすぎの目安。
- 一般に0~100で表示され、80以上が買われすぎ、20以下が売られすぎの目安。
(2) 一般的な使い方
- ラインのクロスで売買判断
- ストキャスティクスは、2本のライン(%Kと%D)を表示させることが多い。
- たとえば「80以上の高い位置で%Kが%Dを下抜けしたら“売り”検討」というのが典型的なシグナル。
- ダイバージェンスの確認
- RSI同様に、値動きとの乖離(ダイバージェンス)を見る分析も可能。
- RSI同様に、値動きとの乖離(ダイバージェンス)を見る分析も可能。
(3) 注意点
- レンジ相場との相性は良いが、強いトレンド相場ではダマシが多い
- 上昇相場でずっと80以上に張り付いたまま落ちない(売りサインが出ても下がらない)ケースがしばしば。
- 過剰に早いシグナルを出しやすい
- 感度が高い分、ダマシも多い。
- 慣れてきたら、スロー・ストキャスティクスや期間調整でノイズを減らす工夫もできる。
4. トレンド系×オシレーター系の組み合わせ例
(1) 移動平均線 + RSI
- トレンドの方向は移動平均線で把握(MAが上向きなら買い目線)。
- そのうえで**RSIが30付近の“売られすぎ”**に近い値に落ちたタイミングを“押し目”とみなして買いエントリー、等。
- トレンドに沿った逆張りなので、成功率が比較的高くなることが多い。
(2) ボリンジャーバンド + ストキャスティクス
- ボリンジャーバンドの±2σを抵抗帯とみなし、ストキャスティクスの80/20と合わせて「そろそろ反発しそうだな」と狙う。
- ただし、強いトレンド時は±2σを何度も突き抜ける可能性があるため、損切りラインは明確に設定。
(3) トレンド×オシレーター×プライスアクション
- たとえば「移動平均線が上向き → RSIが50付近から上に反発 → ローソク足でブレイクアウトの動き」といった複合的な根拠を重ねる。
- 各インジケーターの得意・不得意を補い合い、ダマシを減らす意図があります。
5. オシレーター系のメリット&デメリット
メリット
- 買われすぎ・売られすぎの客観的な目安がわかる。
- 相場の勢いが弱まっているサイン(ダイバージェンスなど)を先読みできる可能性。
- レンジ相場では非常に有効に機能しやすい。
デメリット
- 強いトレンド相場では機能しづらい(逆張りシグナルが多発して踏み上げられる)。
- 設定期間や感度調整が難しい。短期設定だとシグナルが多すぎ、長期設定だと反応が鈍すぎる。
- ダイバージェンスが出ても必ず反転するとは限らない(タイミングの見極めが難しい)。
6. まとめ & 次回予告
まとめ
- RSI・ストキャスティクスは、0~100の範囲で“相場が行き過ぎていないか”をチェックするオシレーター系指標。
- 買われすぎ=70や80以上、売られすぎ=30や20以下がひとつの目安。
- ダイバージェンス(価格と指標の動きが乖離)は、トレンド転換のヒントになることがある。
- トレンド系指標と組み合わせて、トレンド相場では順張りの押し目・戻り目を、レンジ相場では逆張りを狙うなど使い分けると効果的。
- **自動売買(EA)**でもよく使われるが、調整次第でシグナルの質が大きく変わるので十分な検証が必須。
次回(DAY 10)のテーマ:MACD – トレンドと勢いを同時にチェック
- オシレーター系のRSI・ストキャスティクスに続き、次はトレンド系とオシレーター系の“ハイブリッド要素”を持つMACDを学びます。
- トレンドの方向と勢い、そしてダイバージェンスによる転換シグナルなど、多角的に使える人気指標です。
- このあたりのインジケーターを総合的に理解すると、裁量トレードでも自動売買でも大きな武器になるでしょう。ぜひお楽しみに!
自動売買に興味がある方は↓コチラもよろしくお願いします。
https://www.gogojungle.co.jp/users/147322/products
お役に立ちましたら、「続きを読む」を押して頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
×![]()


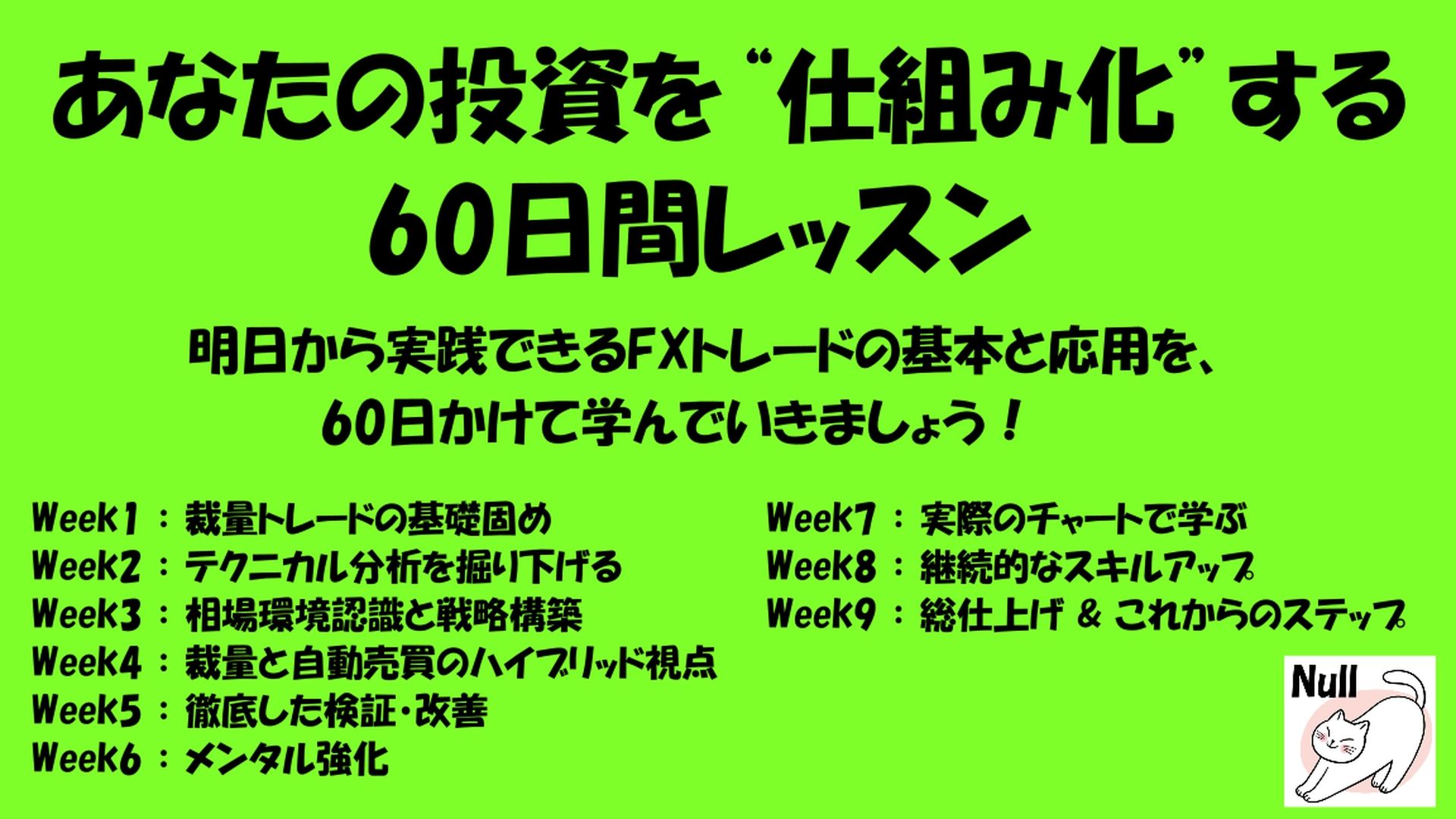
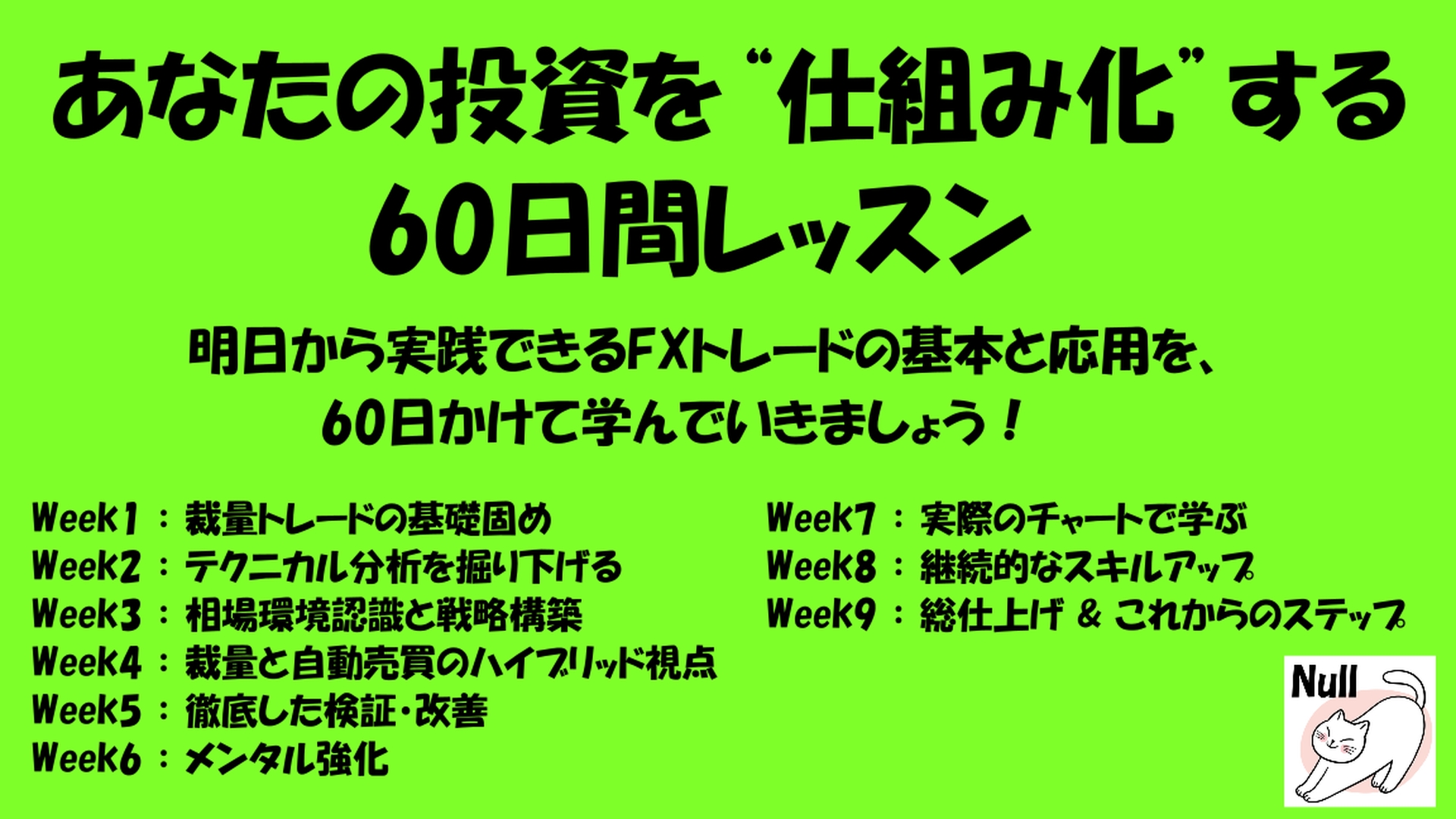
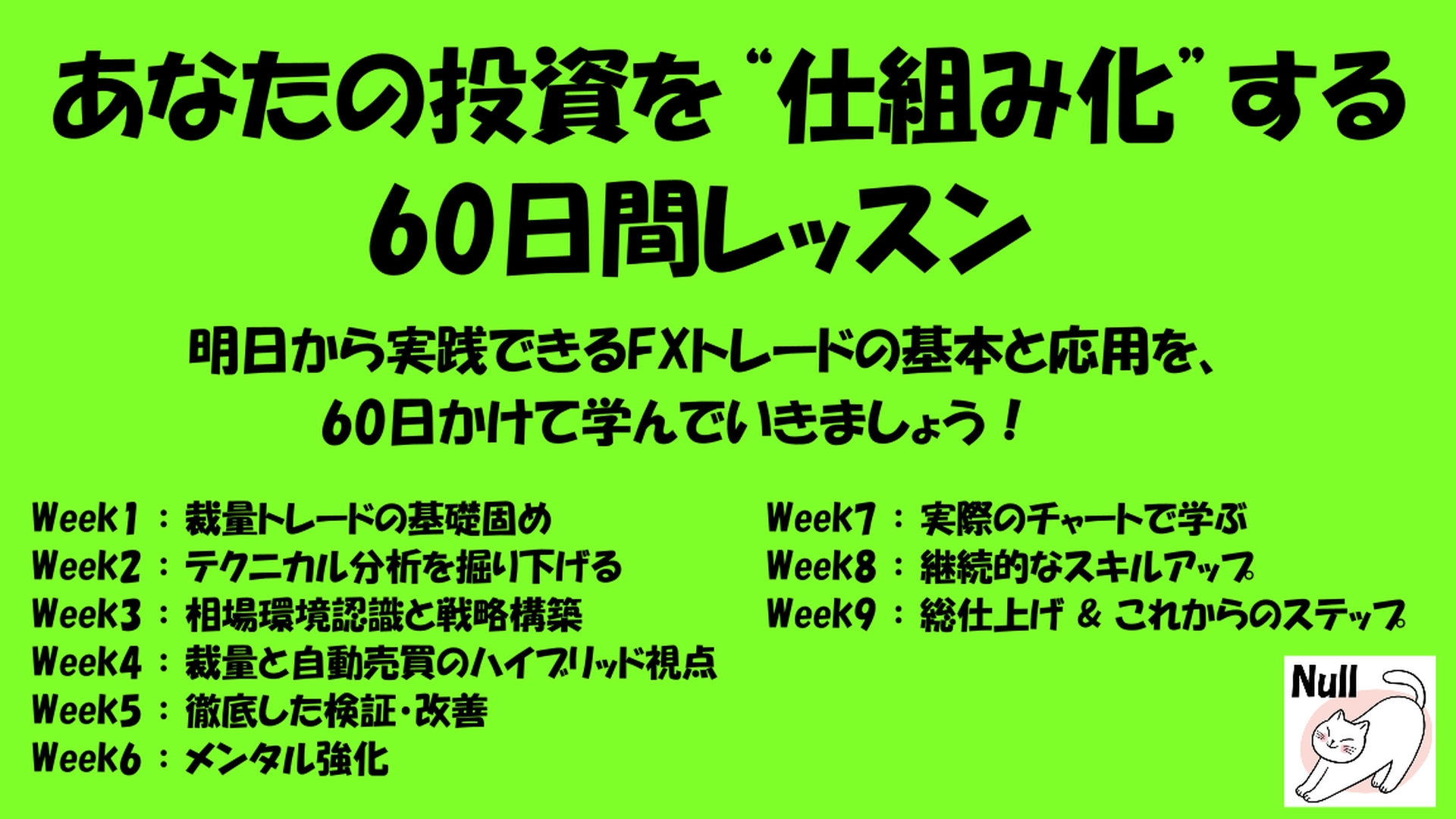
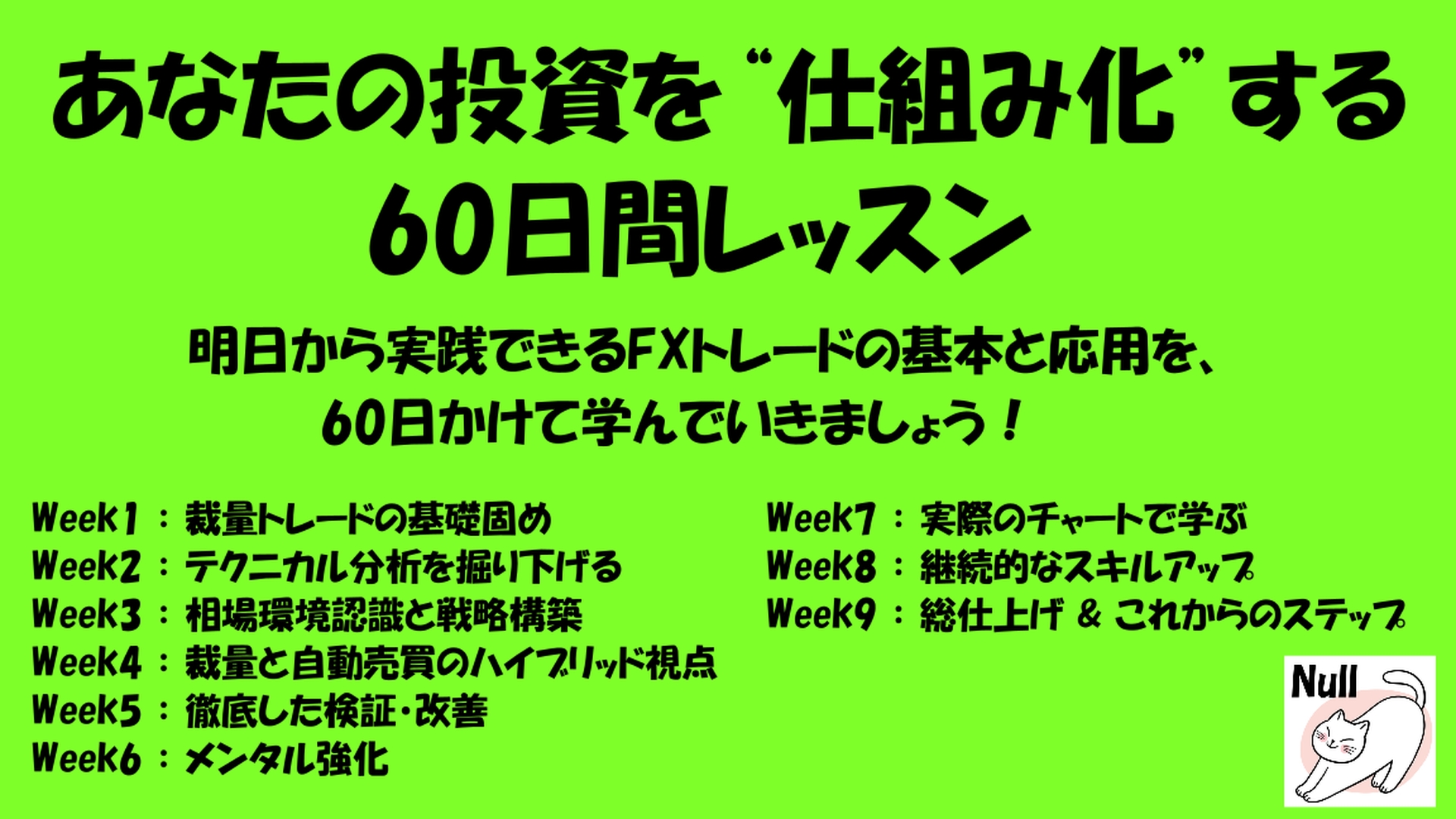
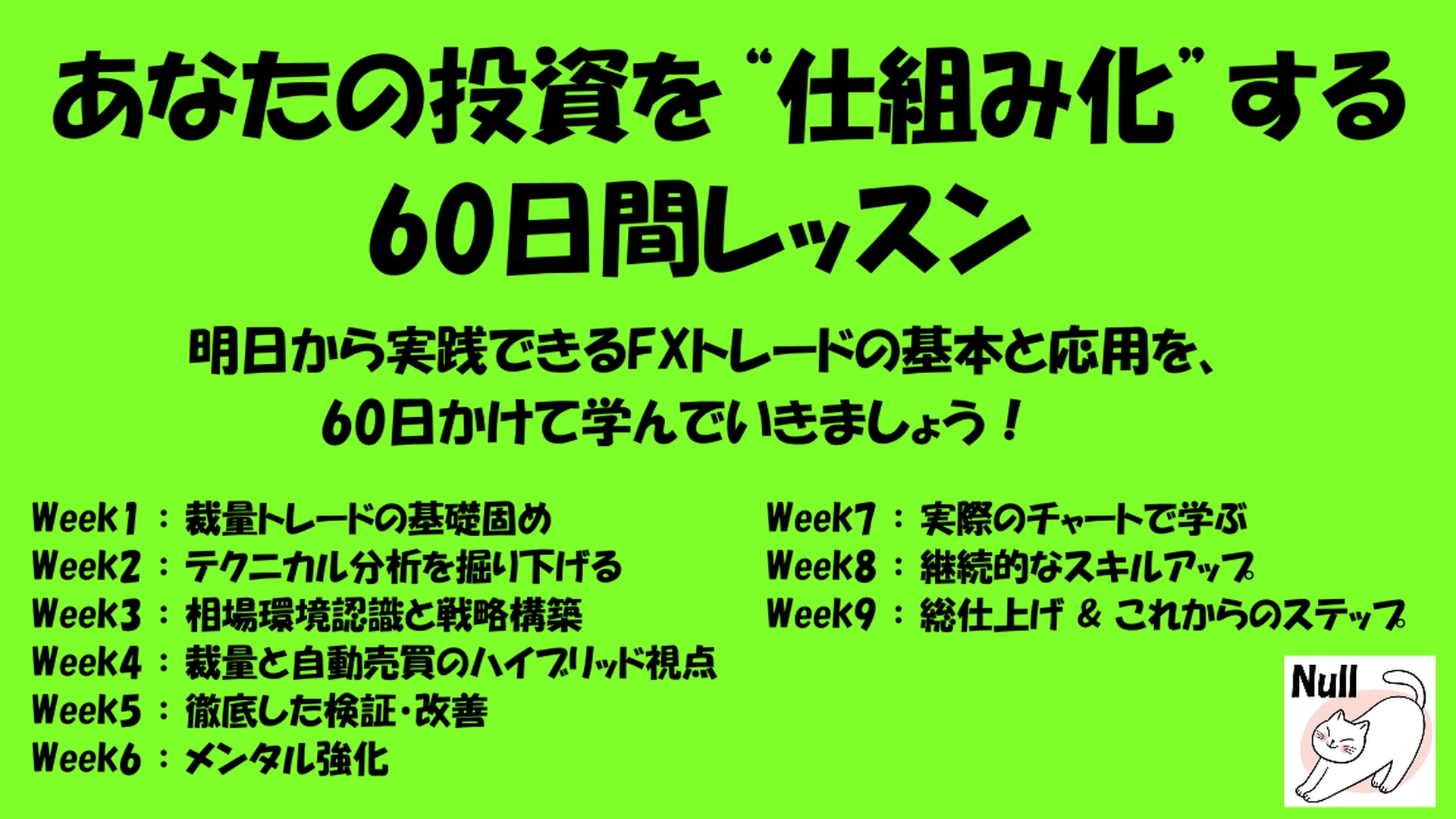
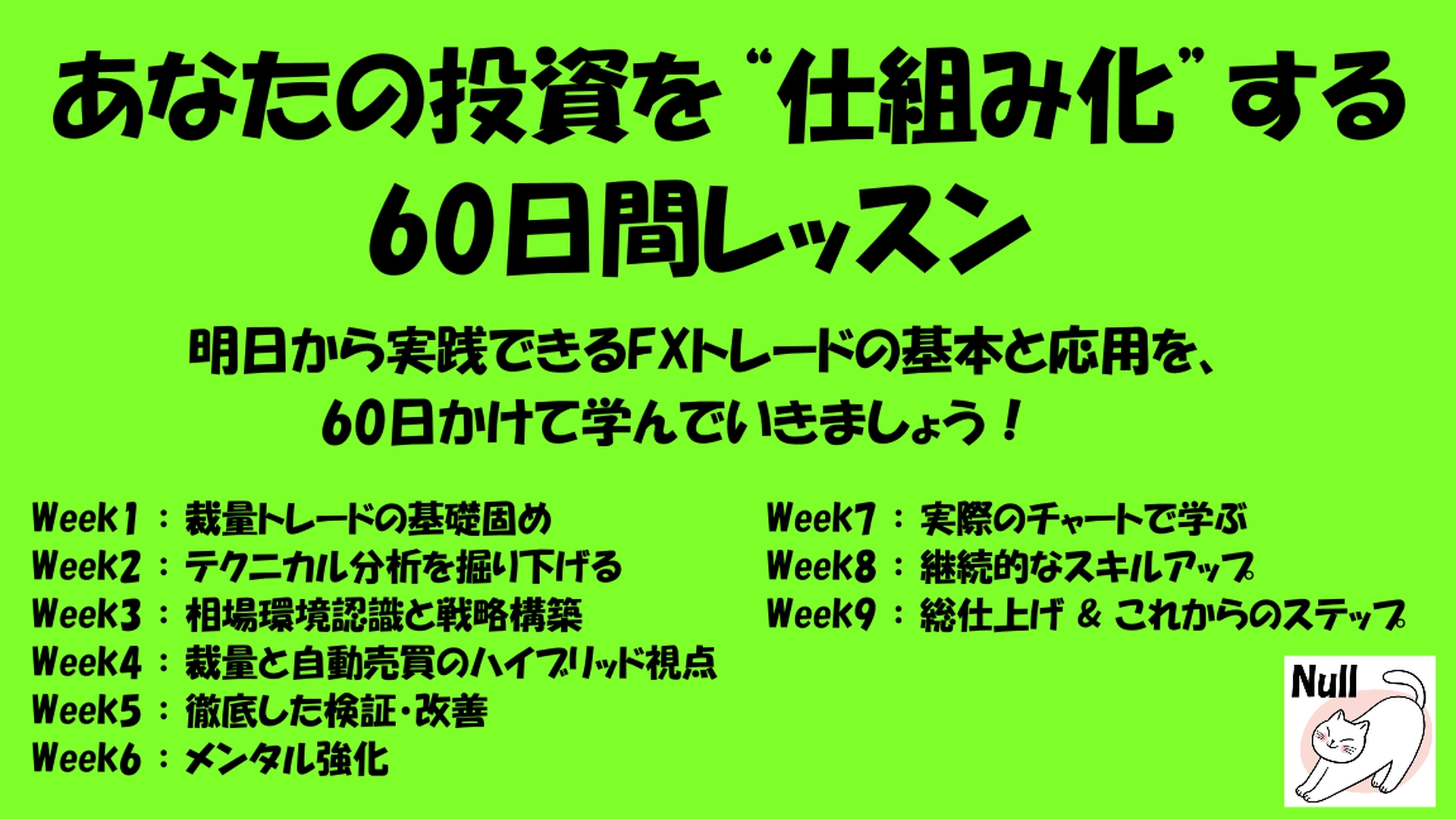
Is it OK?